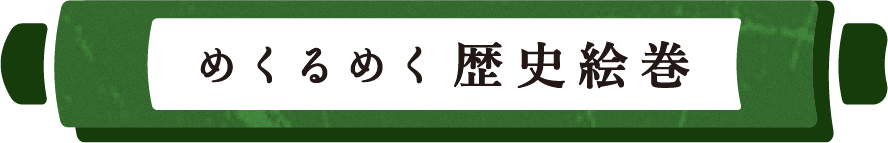
万葉・平安時代
593年
聖徳太子が摂政となる
607年
小野妹子を隋に送る(遣隋使)
唐臼山古墳(大津市)現存 小野妹子の墓と伝わる。
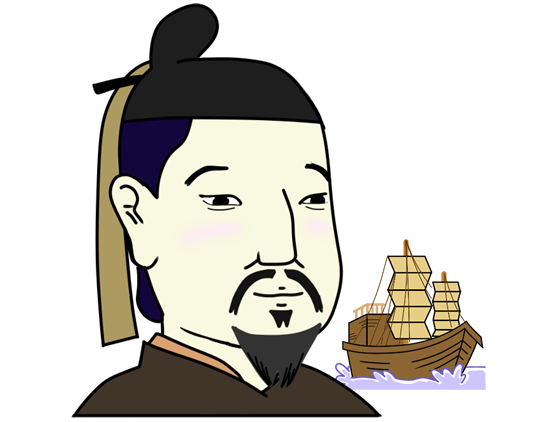
630年
遣唐使の始まり
第1回遣唐使の犬上御田鍬は滋賀(犬上郡)出身。
645年
大化の改新
663年
白村江の戦い
この戦いに敗れた1,000人余りの百済人が滋賀に移り住む。
667年
中大兄皇子(のちの天智天皇)が近江大津宮へ宮を移す

672年
壬申の乱
瀬田唐橋(大津市)が最終決戦地。
710年
平城京に都を移す
742年
紫香楽宮(甲賀市)の造営開始
743年
聖武天皇が紫香楽宮で「大仏造顕の詔」を発し、造立を開始する
745年
紫香楽宮に遷都(都だったのは約半年のみ)
この頃、近江国庁(大津市)がつくられる
747年
聖武天皇の発願により石山寺(大津市)が創建される
平安時代に紫式部は石山寺で源氏物語を起筆したと言われる。
752年
東大寺大仏完成
788年
最澄が比叡山に一堂を建立(延暦寺の前身)(大津市)

794年
平安京に都を移す
815年
嵯峨天皇の唐崎(大津市)行幸の際、茶のもてなしを受ける(日本で最初の喫茶の記録)
993年
天台宗が山門(延暦寺)と寺門(園城寺(三井寺))に分かれる
1180~85年
源平の争乱
1174年 牛若丸が鏡(竜王町)で元服し、源義経になったと伝わる。 1184年 木曽義仲が粟津(大津市)で戦死。
1184年 木曽義仲が粟津(大津市)で戦死。
1185年 平家終焉の地(平宗盛が斬首された場所)は野洲市大篠原。
1185年
源頼朝が守護・地頭をおく
1187年 佐々木定綱が近江守護となる。
沙沙貴神社本殿【県指定有形文化財】(近江八幡市)現存 -佐々木源氏、全国の佐々木姓の発祥の地。
1192年
源頼朝が征夷大将軍になる
1194年 源頼朝の寄進により石山寺に多宝塔が建てられる(建立年代が分かっている多宝塔では日本最古)。
1221年
承久の乱
瀬田唐橋(大津市)現存 が合戦地の一つ。
この頃、信楽焼が始まる。

1338年
足利尊氏が征夷大将軍になる
バサラ大名・京極道誉が活躍。
戦国時代
1467~77年
応仁の乱

1487~88年
9代将軍足利義尚が六角氏を討つために鈎(栗東市)に陣をおく(陣中で死亡)
1528~31年
12代将軍足利義晴が京の兵乱を避け、朽木(高島市)に滞在
1543年
ポルトガル人が鉄砲を伝える
1560年 この頃、国友(長浜市)で鉄砲の生産が始まる。
1549年
ザビエルがキリスト教を伝える
1581年 日本最初のセミナリヨ(神学校)は安土城下(近江八幡市)につくられた。
1571年
織田信長による延暦寺焼き討ち。明智光秀が坂本城を築く(大津市)
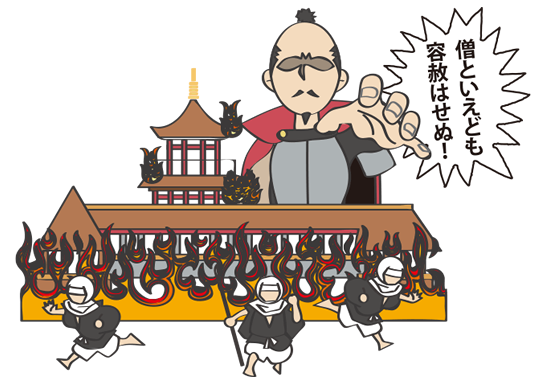
1573年
織田信長が室町幕府をほろぼす
1573年
小谷城の戦い(織田信長により浅井氏滅亡)
1576年
安土城築城開始・安土城が信長の天下布武の拠点に

1582年
本能寺の変

1583年
賤ヶ岳の戦い(長浜市)に勝利し、秀吉が信長の後継となる
1590年
豊臣秀吉が全国を統一する
1600年
関ヶ原の戦い
長浜市出身の石田三成(佐和山城主)が西軍を率いて戦う。

江戸・幕末・近代
1603年
徳川家康が征夷大将軍になる
1603年
秀吉の築いた大坂城の建物が竹生島の宝厳寺に移築される
1604年
彦根城築城開始(天下普請)

1635年
参勤交代の制
草津宿本陣【国指定史跡】(草津市)現存
本陣は街道上の大名らの宿泊・休憩場所で、
一般の人は利用できなかった。この頃、近江聖人・中江藤樹が活躍(陽明学)。
1690年
松尾芭蕉が幻住庵(大津市)に入る

1716年~
徳川吉宗の享保の改革
1787年~
松平定信の寛政の改革
この頃、近江商人が活躍(八幡・日野・五個荘・高島)。 また、東海道五十三次の浮世絵で有名な歌川広重は、近江八景の浮世絵も制作し、人気を博した。
また、東海道五十三次の浮世絵で有名な歌川広重は、近江八景の浮世絵も制作し、人気を博した。
1841年~
水野忠邦の天保の改革
1842年 甲賀・野洲・栗太郡の農民による天保一揆。
1858年
大老井伊直弼が日米修好通商条約を結ぶ
彦根藩主井伊直弼は、17歳から32歳までの15年、彦根城下の屋敷で下積み時代を過ごしていた。
1867年
大政奉還・王政復古の大号令
1871年
廃藩置県
1872年
「滋賀県」の誕生
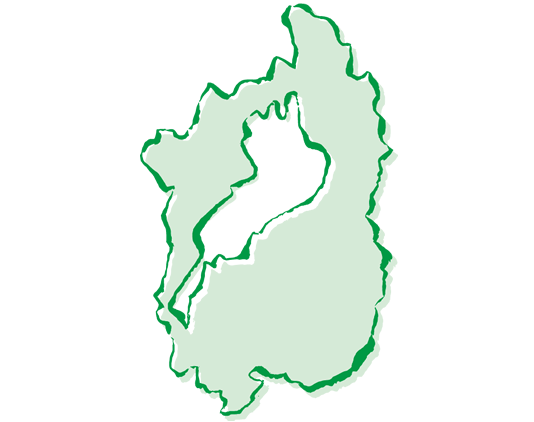
1880年
大津-京都間の鉄道開通
1882年
長浜敦賀間の鉄道開通(柳ヶ瀬トンネル区間除く)長浜大津間は鉄道連絡船が就航し、京都まで結ぶ
1889年
大日本帝国憲法発布
1890年
琵琶湖疏水が完成(第一疏水)
1891年
大津事件(ロシア皇太子が大津市で襲われる)
1894~95年
日清戦争
1904~05年
日露戦争
1905年
ヴォーリズ来日(滋賀県を中心に活躍したヴォーリズは、県内にも多くのヴォーリズ建築を築く) 瀬田川(南郷)洗堰ができる
